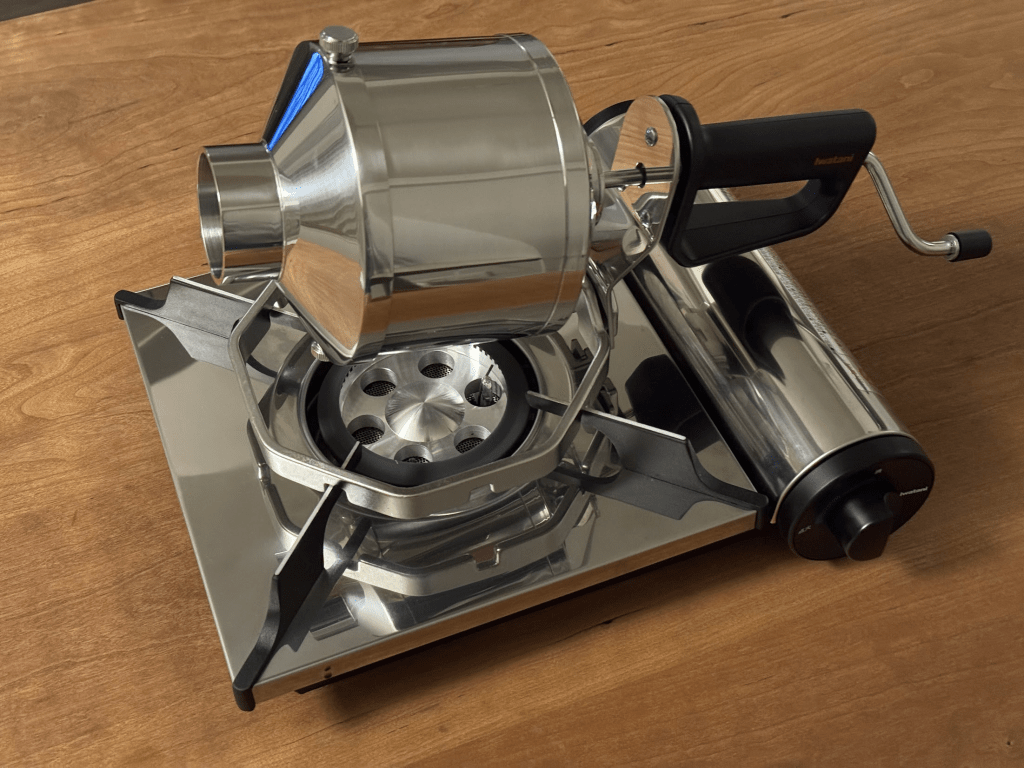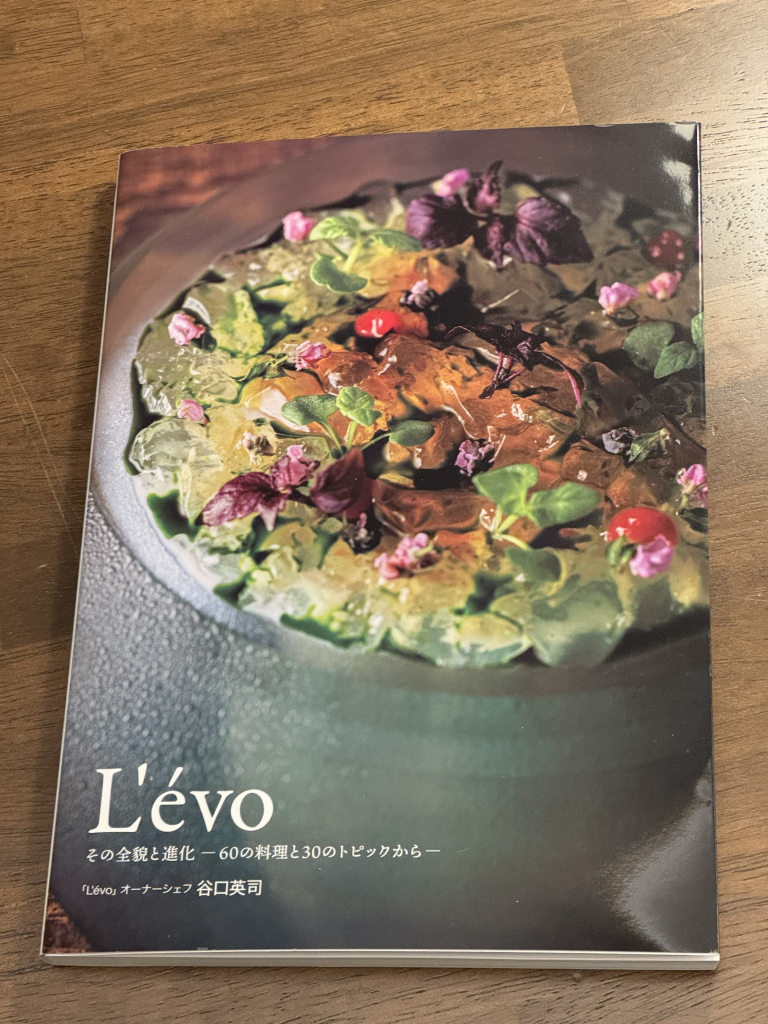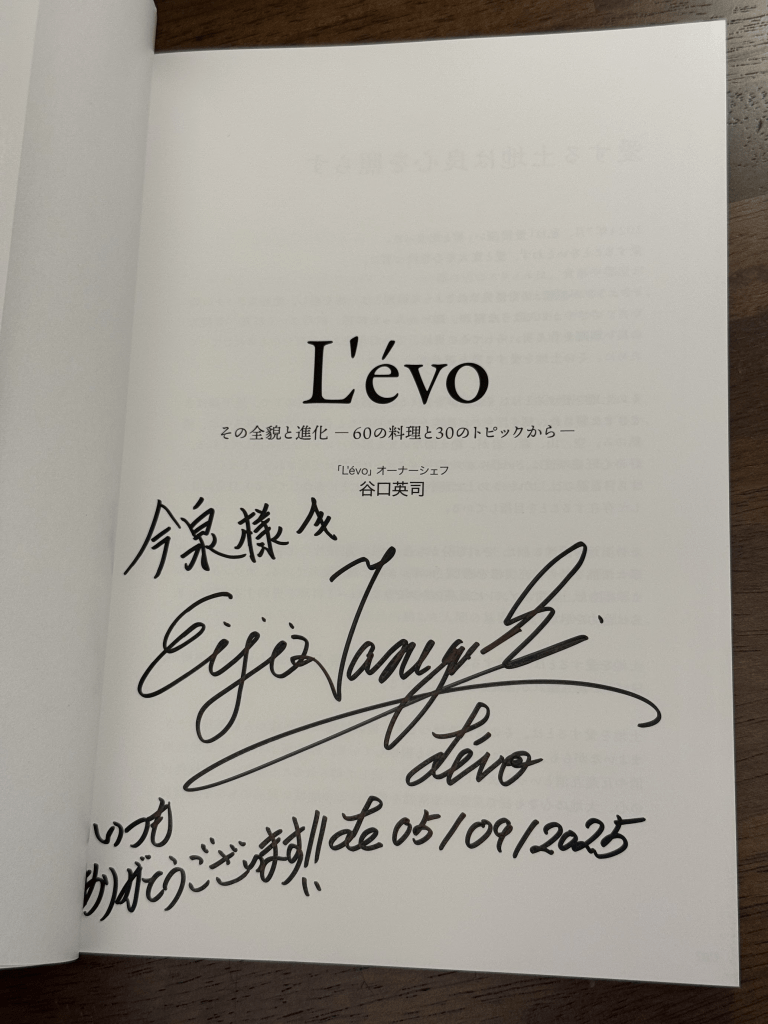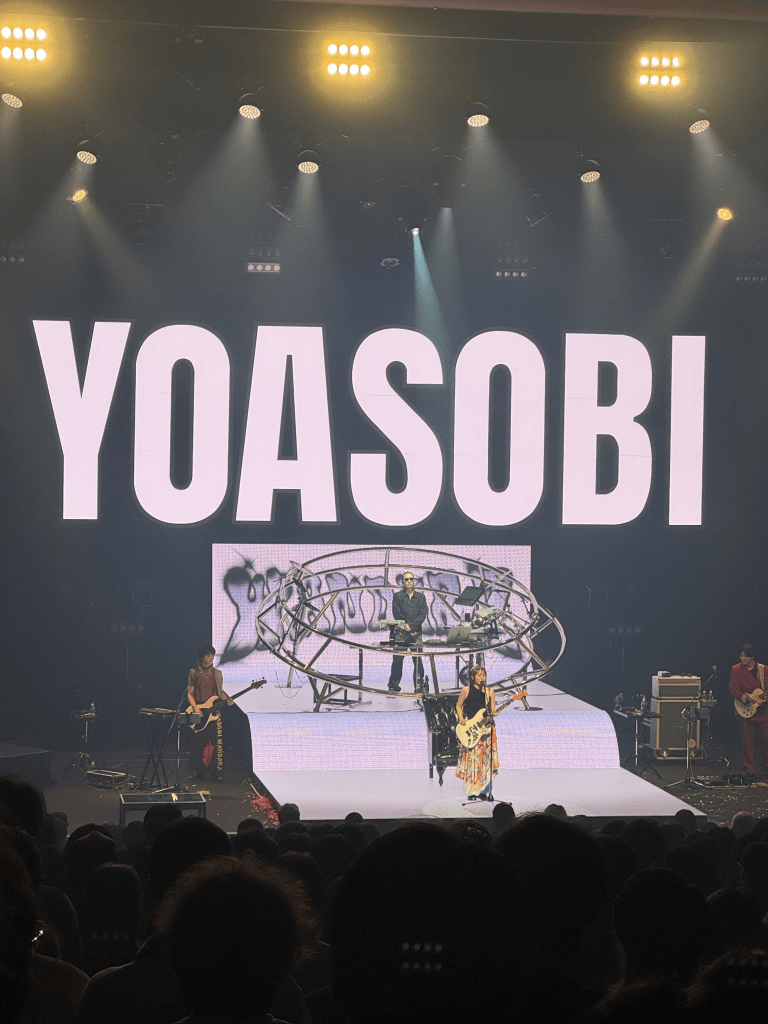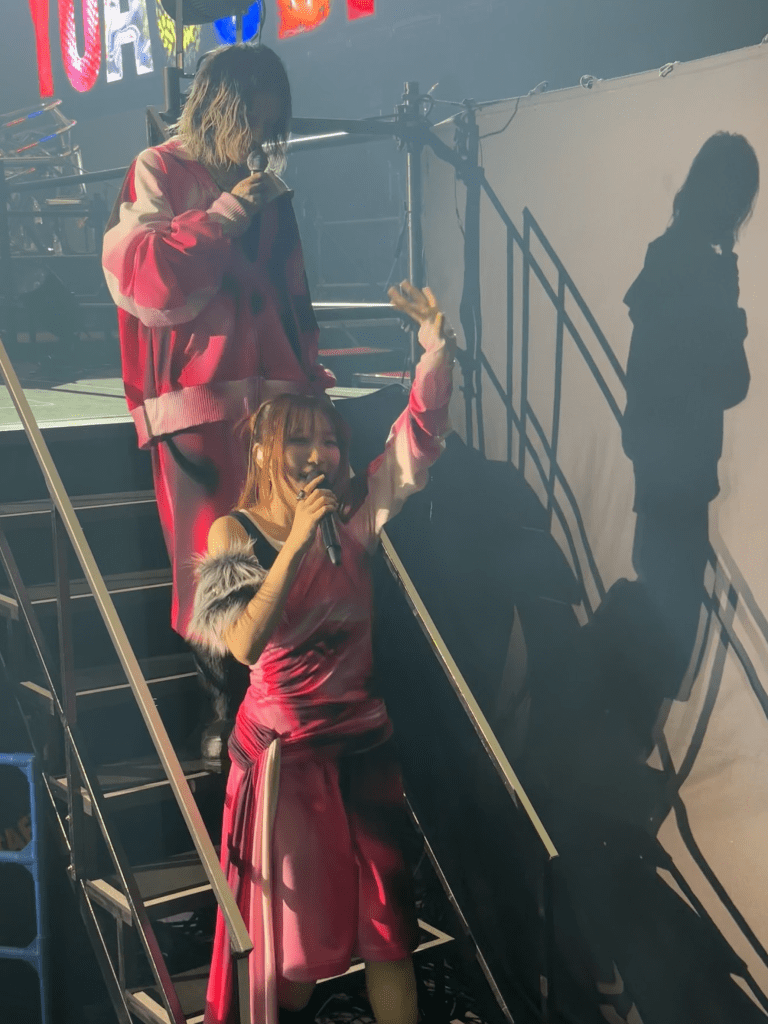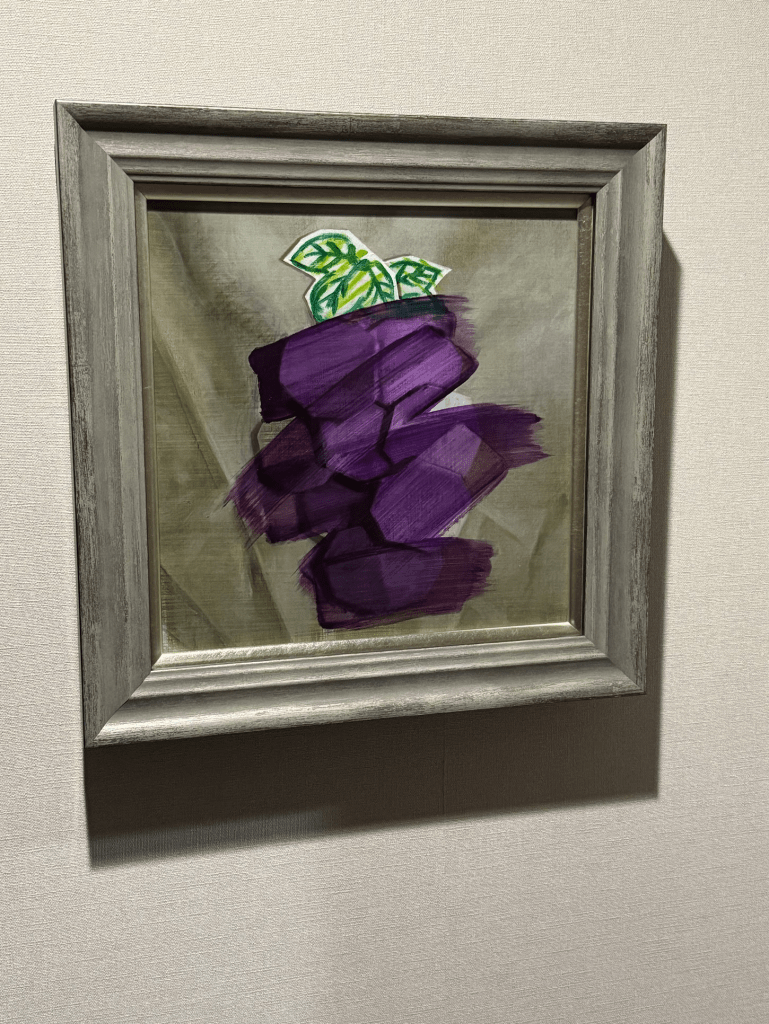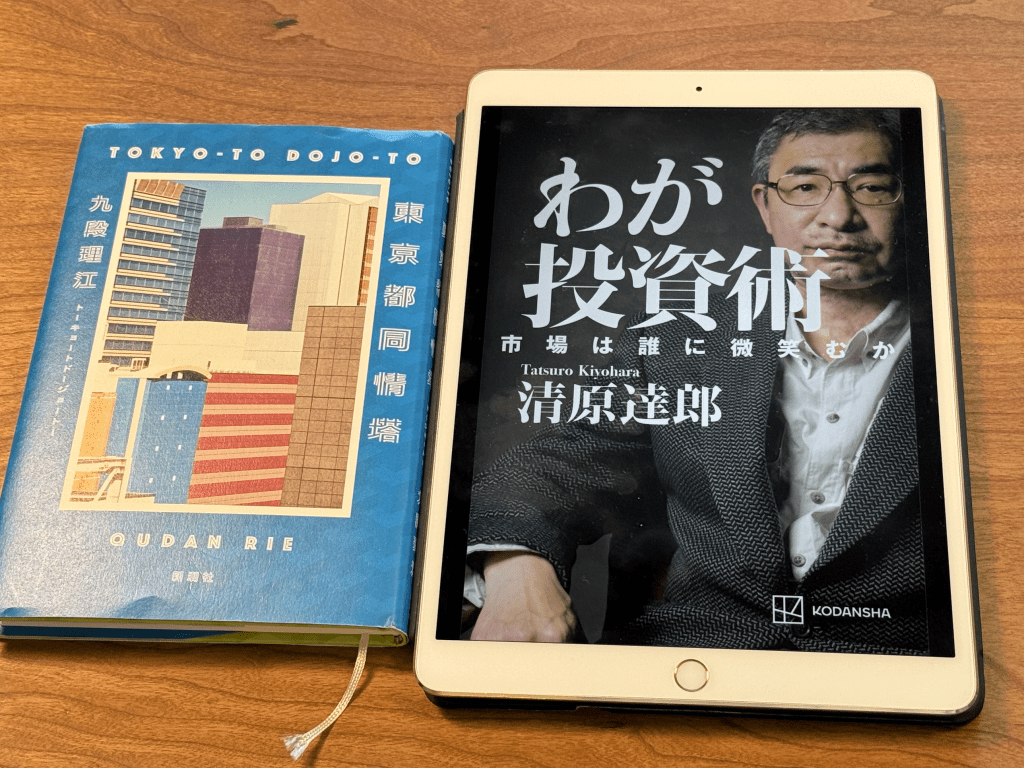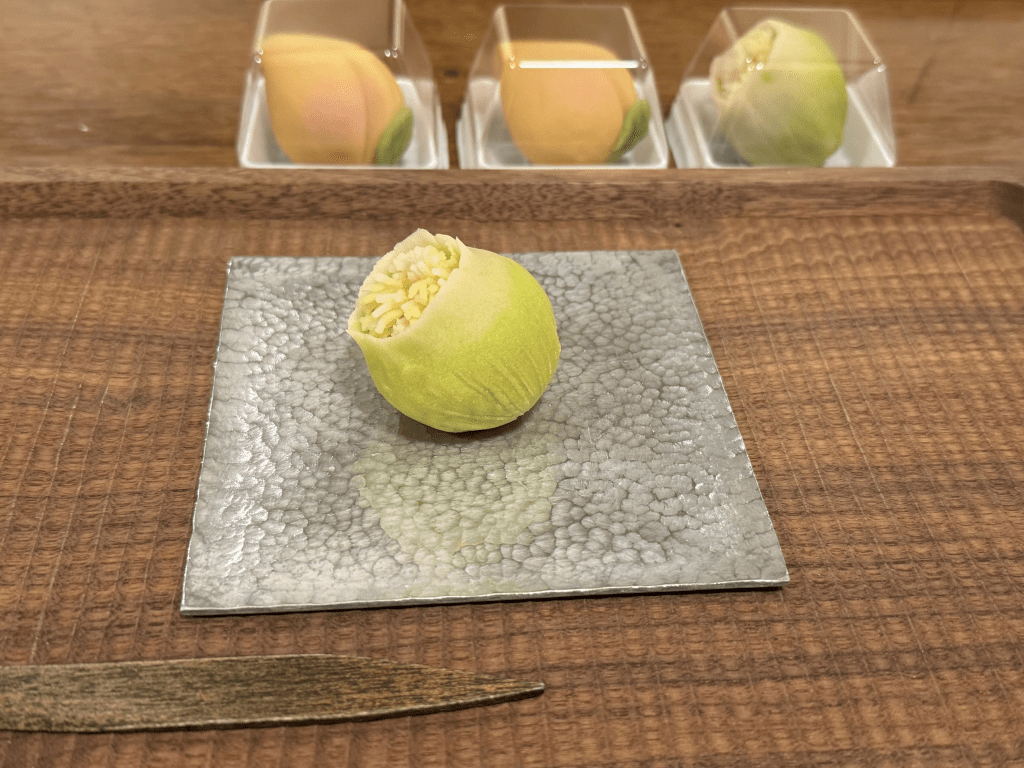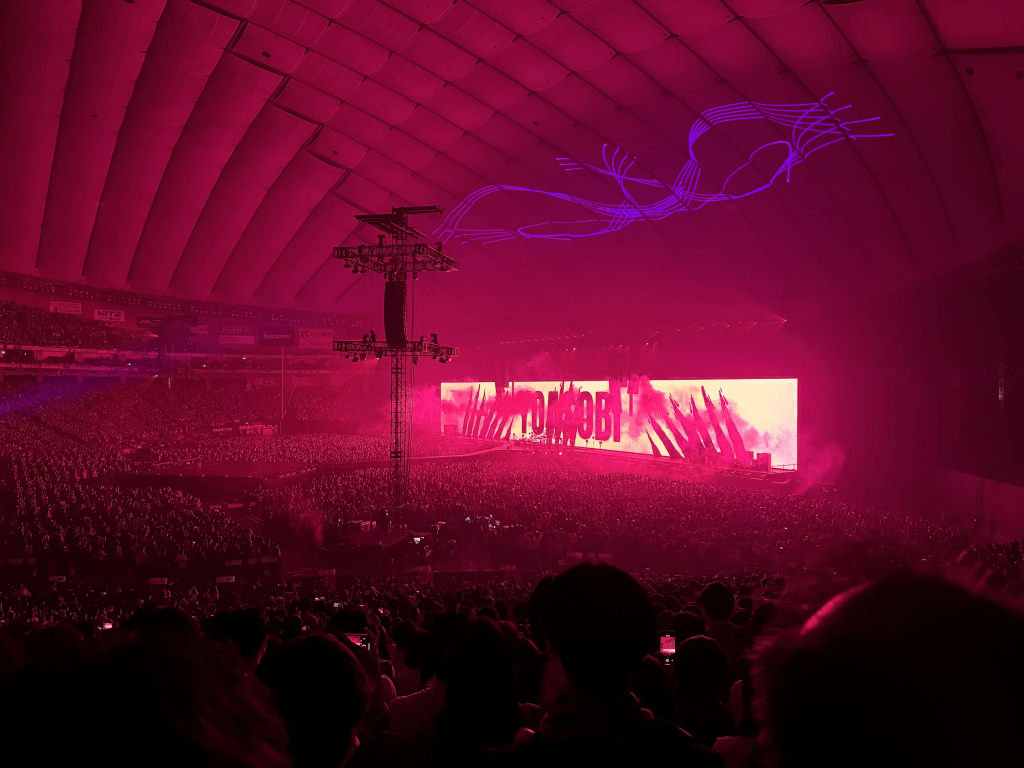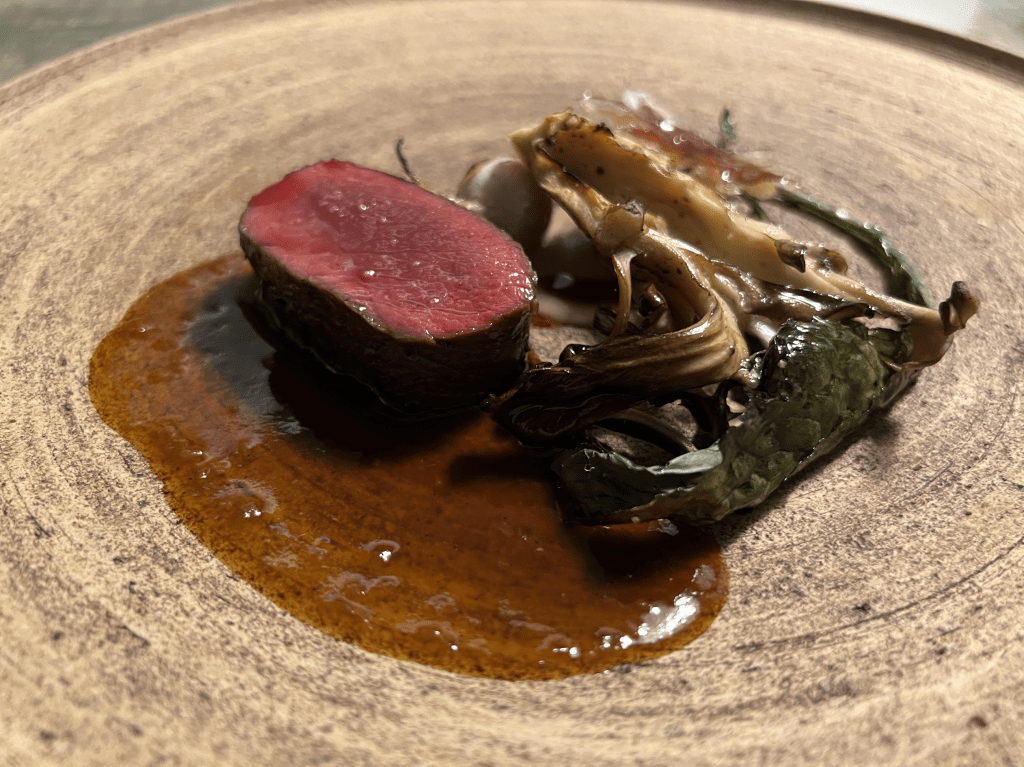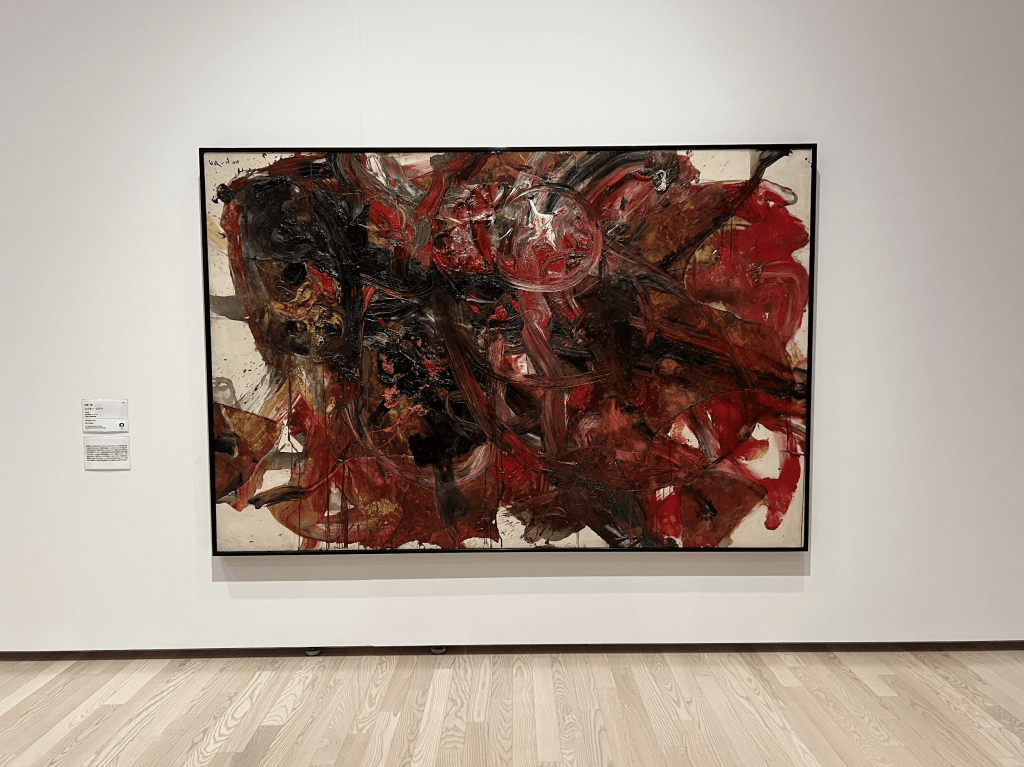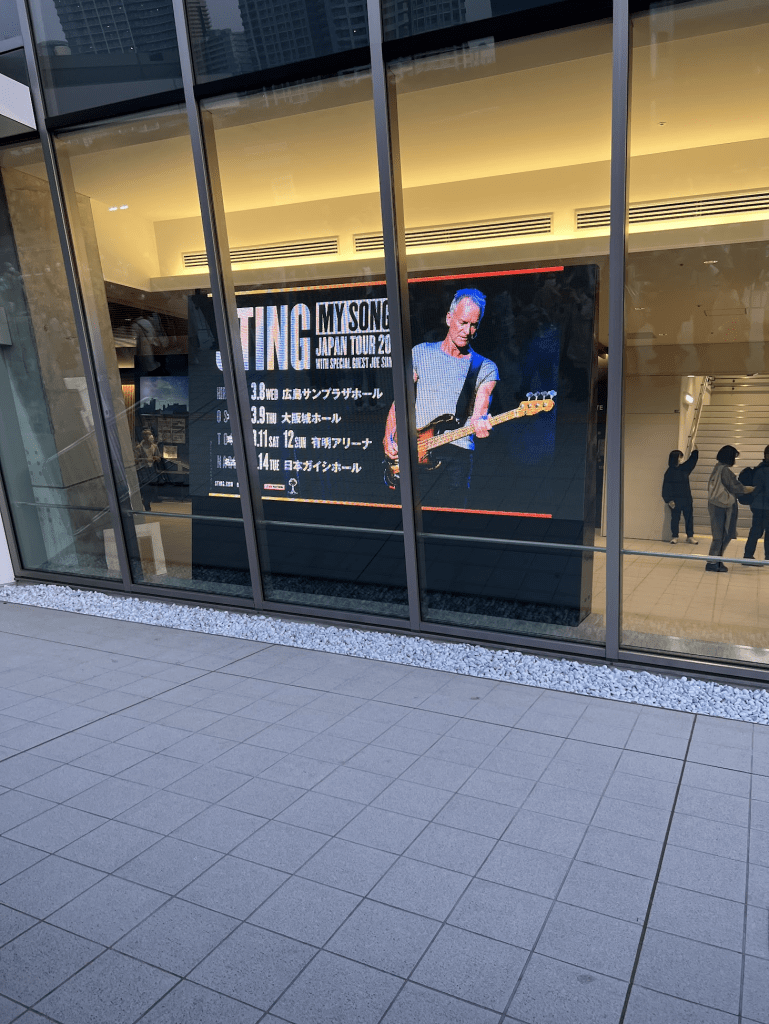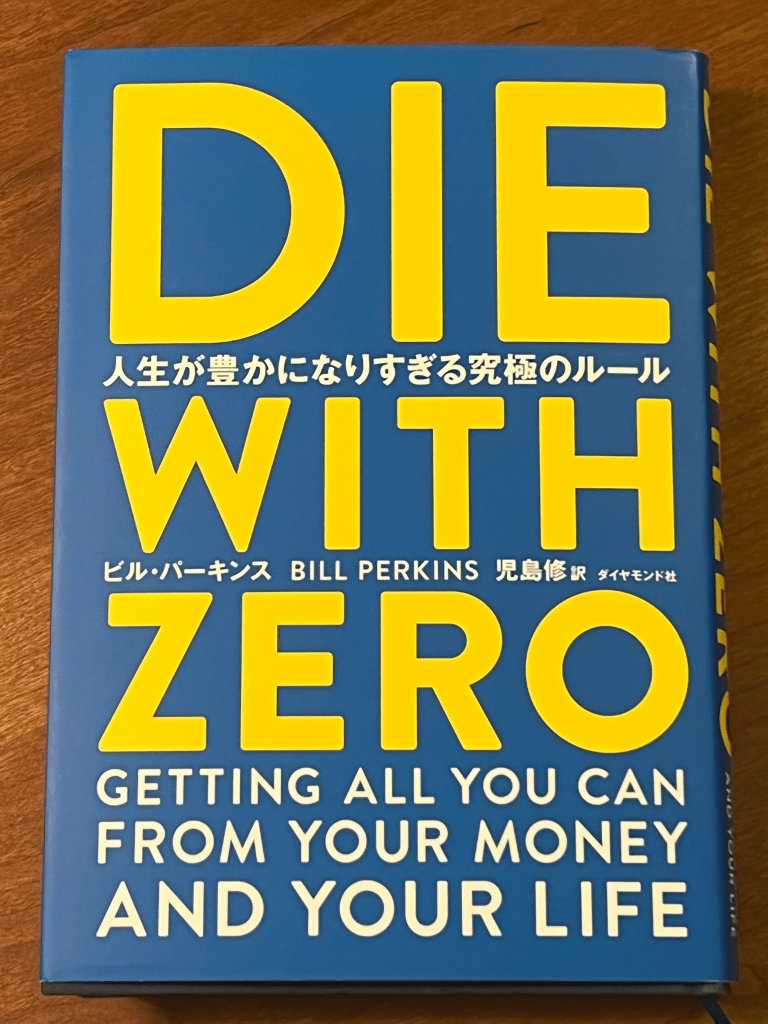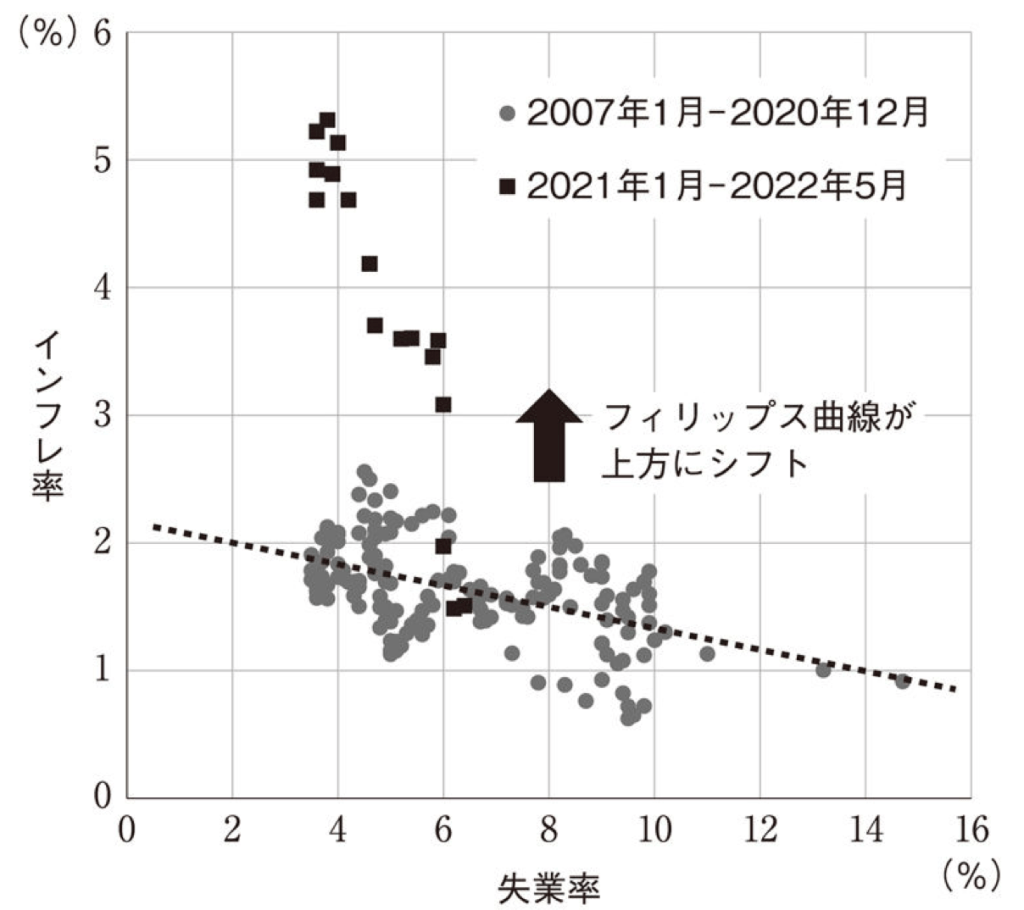『ジョブ理論』は、誰もが知っているであろう『イノベーションのジレンマ』を書いたクリステンセンの著書。それなりに有名だけど、イノベーションのジレンマほど有名ではないと思う。
ジョブ理論では、人々の購買の行動を「人は進歩するために商品・サービスを生活に引き入れる」と捉える。ここで「進歩」というのは人生でゴールに向かって進む行為を表していて、「ある特定の状況で人が成し遂げようとする進歩」をジョブと定義している。
ジョブは、よく使われる「ニーズ」よりもっと具体的で、なぜある特定の解決策が選ばれたかの理由が明確であるとされる。ジョブ理論では、ある商品・サービスを選ぶことを「雇用する」とよび、使うのをやめることを「解雇する」と呼ぶ。
と言っても、なんのことだか分からないと思うので、本書で出てきたジョブの例を(たくさん)列挙したいと思う。
ミルクシェイク (朝の通勤時)
長く退屈な朝の車での通勤中、気を紛らわせるものがほしい。さらに、10時から始まる会議のあいだに空腹を感じないように、小腹を満たせるものがいい。
このジョブがジョブ理論が作られたときの話で一番有名なエピソードだと思う。ジョブ理論の話になったとき、「あー、ミルクシェイクの」といえば、分かってる風にみえるはず。ちなみに、このジョブの競合相手は、 バナナ、ベーグル、ドーナツ、栄養バー、スムージー、コーヒー、など。
ミルクシェイク (夕方に子供と帰宅時)
子どもにいい顔をしてやさしい父親の気分を味わう
同じ商品、同じ顧客でも状況が違うとその商品が雇用されるジョブも異なる。ジョブが異なるので、この場合に適したミルクシェイクは朝とは異なるものになり得る。例えば、サイズは半分でいいかもしれない。このジョブの競合相手は、玩具店に立ち寄ること、自宅でバスケットボールをして子どもと遊ぶこと、など。食べ物である必要もない。
スナップチャット
口うるさい両親に邪魔されずに連絡をとり合いたい
このジョブは若者はいつの時代も持っていたジョブで、昔は、学校でメモを渡す、自室まで電話のコードを引っぱっていく、などが雇用されていたが、時代と共に若者に選ばれるソリューションは変わっていく。
サザンニューハンプシャー大学(SNHU)の通信過程
学び直しのジョブ。将来のキャリアアップのために今より立派な学歴が必要。青春の再経験は必要ない。求めるものは、利便性、サポート体制、資格取得、短期修了。
通信過程の学生の平均年齢は30歳、仕事と家庭へのコミットメントに加えて勉強の時間を捻出しようとしている。このジョブの最大の競合は「無消費」つまり、この顧客が大学で勉強することを諦めてしまうこと。SNHUはできる限り応募者が脱落しないようにプロセスを改善することで大きく成長した。
企業向けトレーニングサービス (フランクリン・コヴィー)
経営幹部に社内教育が必要不可欠であると知ってほしい。社内教育部門が会社の長期的なゴールに不可欠であると認めてほしい。
これは大企業向けのB2Bの例。大企業でトレーニングコースの導入選定をしている人事部門の人(サービスの購入者)が解決したいジョブは何かという話。
クイックブックス(会計ソフト)
公認会計基準の複雑な仕組みを知りたくない。できるだけ楽に入出金したい。
機能を追加すればいいわけではないという話。このプロダクトもB2Bだが、小さい会社がターゲット。顧客は会計にできるだけ時間を使いたくないと思っている。競合相手は、帳簿をつけるためだけに人を雇う、スプレッドシートを使って帳簿を組み立てる、靴箱に領収書を放り込んで忘れてしまう、など。クイックブックスは、他の会計ソフトと比べて半分の機能しかもっていないソフトを倍の価格で売り出し成功した。
以下、ジョブの例のみをずらずらと列挙したい。
マーガリン
飲み込みやすいようにパンの耳や皮を湿らせる何かがほしい
調理中に食材を焦がさないようにする
小さい家への住み替えにフォーカスした建築会社
人生にとって深い意味をもつ何かを手放すことの不安を感じずに小さい家に転居したい。
オンライン教育ビデオ (カーン・アカデミー)
核となる概念を楽しく学びたい。両親に教えてもらったり、教師に補修を頼んだりするのはいや。
キンバリークラーク
恥ずかしさを感じず、尊厳を損なわずに、失禁用の商品を購入・使用したい
シンプルなオンラインバンク (INGダイレクト)
目標に向かって貯蓄することのたいせつさを子どもに教え、自分がよい父親だと感じたい
CVSミニッツクリニック
避けたいジョブ: 簡単な診察のあとに、やはり喉頭炎でしたと言われることが分かっている医者のとこへ何時間もかけて出かけること
アメリカンガールドール
(少女のジョブ) 自分の感情を表に出したり、アイデンティティ、自意識、文化的・人種的バックグラウンドを確認し、ついらいことがあっても乗り越えていけるという希望を得る
(母親のジョブ) 母娘で、何世代にもわたる女性たちの暮らしぶりや悩み、強さについて、豊かな会話の機会を持つこと
これは、商品の使用者と購入者が違うジョブを解決しようとしている例。
IKEA
明日までに新居の家具をそろえる必要がある。明後日からは仕事だから
IKEAは必ずしも安くないが何故成功しているかという話。
オンスター (GMの定額制アシスタントサービス)
運転中の心の平安。例えば、初めての場所にいて外が暗くなってきた。安全な道まで早く誘導してほしい。
デザレット・ニュース (ローカル新聞社)
もっと情報通になりたい、自分の知識にもっと自信をつけたい、自分の信念に忠実でありつづけ、家庭や地域社会に変化をもたらしたい。自分の価値観を反映したニュースをつうじて知識を豊かにする
たくさんのジョブの例を見て、分かったような分からないような感じかもしれないが、最後にジョブでない例を見て終わりにしたい。
ユーザーニーズ: ほぼ常に存在して、漠然としている。例えば「私は食べる必要がある」「健康でいたい」「定年後に備えて貯蓄する必要がある」など。
人生の指針: 常に存在し、生きていくこと全般にかかわるテーマ。「よい夫になりたい」「教会のよい信徒でありたい」「学生の勉学意欲を引き出せる存在でありたい」など。
特定のプロダクトでしか解決できないもの: 「350ミリリットルの使い捨て容器にはいったチョコレート味のミルクシェイクがほしい」。よく定義されたジョブはミルクシェイク(夕方)のように、プロダクトをまたがった幅広いソリューションがあり得る。